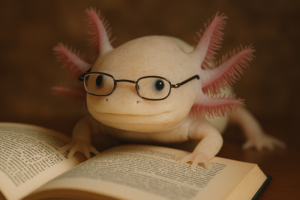冬になるとウーパールーパーが動かなくなり、「冬眠しているのでは?」と不安になる飼い主さんは少なくありません。
しかし、その行動にはきちんとした理由があります。
この記事では、冬場に見られる変化の正体と、命を守るために知っておきたい正しい対応を解説します。
\ ウーパールーパーの飼育に関する /
まとめページは以下より
ウーパールーパーの飼育まとめ
ウーパールーパーは冬眠するのか?

ウーパールーパーはカエルと同じ両生類です。
多くのカエルは冬眠することで有名ですが、ではウーパールーパーも同じく冬眠することはあるのでしょうか?
結論から言うとウーパールーパーは 冬眠はしません。
ただし、水温が低下すると代謝が落ちて活動が鈍くなるため、見た目には「休眠」しているように感じられることがあります。
しかし、冬眠の定義とは明確に異なります。
冬眠の定義
冬眠とは、動物が冬の寒さを乗り切るために、代謝を極端に低下させ、エネルギー消費を最小限に抑えながら長期間休眠状態に入る生理現象です。
代表的な冬眠動物にはクマ、ハリネズミ、ヤマネ、アマガエル、ヒキガエル、カメ、ヘビなどがいます。冬眠中の動物は、体温が大幅に下がり、心拍数や呼吸数も極端に低下することで、外部刺激にも反応が鈍くなるか、ほぼ無反応になります。
また、体内に蓄えた脂肪や栄養分をゆっくり消費しながら、数週間から数か月間の長期的な休眠状態を維持します。気温が上昇すると冬眠状態から目覚め、再び通常の活動に戻ります。
ウーパールーパーのは「冬眠ではない」理由

ウーパールーパーの場合、冬眠のように見える行動を取ることはありますが、厳密には「低温休眠」に近い状態です。
ウーパールーパーは変温動物のため、水温の変化に応じて体温や代謝が変化します。
特に水温が10℃以下になると代謝が極端に低下し、餌を食べる量が減ったり、動きが鈍くなったりします。
ただし、完全に代謝が停止したり、意識レベルが極端に低下する冬眠状態にはなりません。
10℃以下ではほとんど動かなくなることがありますが、この状態は「冬眠」ではなく、単に低水温の環境で代謝が落ちているだけです。
冬眠と類似する現象
冬眠と似ている概念にはいくつかのものがあります。
「休眠(きゅうみん)」は冬季だけでなく、乾季や夏季などの環境が不適切な時期にも活動を停止する現象で、昆虫や植物に多く見られます。
「低温休眠(低代謝状態)」は、冬眠と似ているものの代謝が完全には停止せず、最低限の活動を維持している状態を指します。
ウーパールーパーが低水温下で見せる行動はこの低温休眠に該当します。
「疑似冬眠(仮冬眠)」は、本来冬眠しない種が環境の急変によって一時的に代謝が低下する現象ですが、これもウーパールーパーには該当しません。
ウーパールーパーの冬の行動と注意点

冬場に水温が下がると、ウーパールーパーは活動が鈍くなり、底でじっとしていることが増えます。
特に水温が5℃~10℃くらいになると、代謝は極限まで落ち、餌を食べるペースも大幅に減少します。
水温が4℃以下になると危険な状態になり、低体温で衰弱死するリスクが高まるため、注意が必要です。
ウーパールーパーの理想的な水温は18℃~20℃程度であり、冬場でもこの水温をキープすることが健康維持のために重要です。
水温が10℃を下回る場合はヒーターを使用して適切な水温を保ちましょう。
また、水温が下がると消化機能も鈍くなるため、餌の量や頻度も調整が必要です。
活動が鈍いからといって異常とは限りませんが、長期間低水温が続くと免疫力が低下し、病気のリスクが高まります。
カエルと同じ両生類だからと冬眠させるのは危険ですから絶対にやめてください。
冬場に「異常」と「正常」を見分けるポイント

冬になると動きが鈍くなるウーパールーパーですが、すべてが「正常な低温反応」とは限りません。
ここでは、飼育者が特に迷いやすい「様子見でよい状態」と「すぐ対処すべき状態」の違いを整理します。
活動が鈍いだけなら問題ないケース

水温が10~15℃前後まで下がると、ウーパールーパーは明らかに動かなくなります。
底でじっとしていたり、物陰からほとんど出てこなかったりするのは、この時期では珍しいことではありません。
呼吸のためにときどき浮上する、外部刺激(掃除や給餌)にはわずかに反応する、といった様子が見られるなら、生理的な代謝低下の範囲内と考えられます。
この状態で無理に刺激したり、餌を与え続けたりする必要はありません。
危険サインとして注意すべき行動

一方で、次のような状態が見られる場合は「冬だから仕方ない」と判断してはいけません。
・エラが明らかに縮み、色が極端に薄くなっている
・浮上せず、長時間まったく動かない
・体を横倒しにしたまま戻らない
・皮膚が白く濁る、ただれる、カビ状のものが付着している
これらは低水温による衰弱や病気の初期症状である可能性が高く、放置すると命に関わります。
特に水温が5℃以下になっている場合は、緊急的な温度管理が必要です。
冬場の給餌は「食べるかどうか」で判断する

冬場は「餌を減らす」のではなく、「食べるかどうかを基準にする」ことが重要です。
水温が下がると消化能力も落ちるため、無理に与えると未消化のまま体内に残り、体調不良の原因になります。
餌を近づけても反応がない場合は、その日は与えず様子を見る判断で問題ありません。
逆に、少量でも自発的に食べるようであれば、消化しやすい餌を控えめな量で与えるようにします。
冬場は「食べない=異常」ではないことを理解しておくことが大切です。
「冬眠させたほうがいい」は誤った情報

ネット上では「冬は冬眠させたほうがよい」「低温で管理するのが自然」といった情報を見かけることがあります。
しかし、飼育下のウーパールーパーに意図的な低温管理や冬眠処置は不要で、むしろ危険です。
野生下とは異なり、逃げ場のない水槽環境では低水温ストレスが蓄積しやすく、免疫力の低下や病気につながります。
冬でも18℃前後を安定して保つことが、もっとも安全でトラブルの少ない管理方法です。
まとめ
ウーパールーパーは冬眠をしませんが、低水温では代謝が落ちて動きが鈍くなります。
大切なのは「冬だから放置」ではなく、「正常な反応か危険なサインか」を見極めることです。
冬場の管理を正しく行い、安心して寒い季節を乗り切りましょう。
\ ついでにこれも読んでいけ。 /
いや、読んでくださいお願いします(土下座)