カエルや爬虫類を飼ったことがある人なら、コオロギが主力のエサとして使われていることをご存じでしょう。
その影響もあり、「ウーパールーパーにもコオロギを与えていいのでは?」と考える人も少なくありません。
見た目はおとなしくても、実は肉食性の強いウーパールーパー。果たしてコオロギはウパのエサとして適しているのでしょうか?
この記事では、ウーパールーパーにコオロギを与えることの可否や注意点について、わかりやすく解説していきます。これから試してみようか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
ウーパールーパーの餌の関連記事一覧
\ ウーパールーパーの飼育に関する /
まとめページは以下より
ウーパールーパーの飼育まとめ
ウーパールーパーにコオロギを与えてもいいの?

「カエルにコオロギを与えるように、ウーパールーパーにも与えていいのでは?」と考える方もいるかもしれません。
たしかに、コオロギはカエルや爬虫類の定番エサとしてよく知られています。
ウパにとってコオロギは野生下では食べることがない
しかし、ここで注目したいのはウーパールーパーが完全な水生生物であるという点です。
同じ両生類であるカエルは、陸上に上がる成体になるとコオロギなどの陸生昆虫を捕食するようになります。
でも、ウーパールーパーは一生を水中で過ごすため、自然界でコオロギのようなエサを目にすることはまずありません。
つまり、ウーパールーパーにとってコオロギは自然なエサではないということです。
与えれば食べる
とはいえ、ウーパールーパーは肉食性が強く、動くものに反応して食いつく習性があります。
そのため、人工的な環境下ではコオロギをエサとして利用することも可能です。
ただし、与え方を間違えると体に負担をかけることがあるため、注意が必要です。
コオロギがカエルや爬虫類で定番エサになっている理由

コオロギは、カエルやトカゲ、ヤモリなど、さまざまな陸生の両生類・爬虫類にとって定番のエサです。
栄養価が高い+動きがある
その理由はとてもシンプルで、栄養価が高く、動きがあることで食欲を刺激するためです。
特に陸上で生活する生き物は、目で動きを追ってエサを認識します。
ピョンピョン跳ねるコオロギはまさに絶好のターゲット。
野生下でも簡単に見つけられる存在であり、飼育下でもその再現がしやすいのです。
入手が容易
また、ペットショップや通販などで手軽に手に入ることも、飼育者にとっては大きなメリット。
栄養バランスの良さ、入手のしやすさ、そして本能を刺激する動き。
この3拍子がそろっているからこそ、コオロギは広く使われているのです。
こうした背景から、「じゃあウーパールーパーにも使えるのでは?」と考える飼育者がいても不思議ではありません。
ただし、先述した通り、ウーパールーパーは一生を水中で過ごす生き物。
自然界でコオロギを捕まえることはほとんどありません。
そのため、「定番エサ」として扱われている他の生き物とは事情が違うことを、改めて理解しておく必要があります。
ウーパールーパーにコオロギを与えるメリット

ウーパールーパーにとって、コオロギは自然なエサではないものの、飼育下で適切に与えればいくつかのメリットが期待できます。
以下にそのポイントをまとめます。
高たんぱくで栄養価が高い
コオロギは動物性たんぱく質が豊富で、ウーパールーパーのような肉食傾向のある生き物にとって、栄養源としては優れています。
特に、成長期の個体や、食欲が落ちて体力が低下しているときなどには、補助的な栄養源として役立つこともあります。
動きがあり、食いつきが良い
ウーパールーパーは動くものに反応して捕食する習性があります。
コオロギはその動きでウパの本能を刺激し、食欲を引き出す「きっかけ」になることがあります。
普段のエサに飽きてしまった個体でも、ピンセットで動きを見せながら与えることで興味を示すことがあります。
食事のバリエーションとして活用できる
毎回同じエサでは飽きてしまう個体もいます。
そんなとき、たまにコオロギのような「変化球」を入れることで、刺激になり、食への関心を保たせることができる場合もあります。
コオロギを与える際の注意点とデメリット
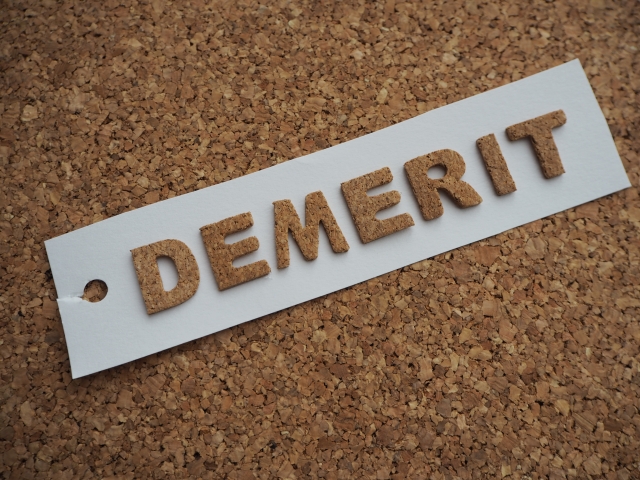
ウーパールーパーにコオロギを与えることは可能ですが、いくつか注意しなければならないポイントやリスクがあります。
メリットだけに目を向けず、以下の点をしっかり押さえておきましょう。
① 消化不良のリスクがある
コオロギの体は外骨格に覆われており、硬い足や羽、殻の部分は消化しにくいです。
特に内臓がまだ未発達な幼体や、小柄な個体にとっては消化に負担がかかる可能性があります。
これが原因で便秘や腸閉塞を引き起こすこともあるため、与える際はサイズを選ぶ・足や羽を取り除くなどの工夫が必要です。
② 水面に浮いて食べづらいことがある
コオロギは水に入れるとすぐに動きが鈍くなり、水面に浮いてしまいます。
ウーパールーパーは水中の獲物に反応する習性があるため、水面に浮いているエサには気づきにくい場合もあります。
そのまま放置すると食べ残されてしまい、水質を悪化させる原因になることも。
こうしたトラブルを防ぐためにも、ピンセットで目の前に持っていくなどの工夫が有効です。
③ 栄養が偏りやすい
コオロギは高たんぱくで優秀なエサではありますが、カルシウムやビタミンなどのバランスは不十分です。
コオロギだけを頻繁に与えてしまうと、栄養の偏りが起き、骨の成長や内臓の働きに悪影響を与えることもあります。
栄養を補うためにコオロギに野菜やカルシウム剤を与えてから食べさせる(ガットローディング)という方法もありますが、手間や管理の面ではやや上級者向けです。
④ 衛生面・寄生虫のリスク
不衛生な環境で育ったコオロギや、野生で捕まえた個体には寄生虫や農薬、雑菌が付着している可能性があります。
これらが原因でウーパールーパーの体調を崩す恐れもあるため、信頼できるショップで購入するか、冷凍処理されたものを使うのが安心です。
コオロギを与えるならどうすべき?【与え方のコツ】
コオロギはウーパールーパーにとって自然なエサではないため、与える際にはいくつかの工夫や注意点が必要です。
以下に、失敗しないための与え方のコツをご紹介します。
コオロギの種類とサイズを選ぶ

市販されているコオロギには主に以下の2種類があります。
- ヨーロッパイエコオロギ(フタホシコオロギ):一般的で扱いやすく、柔らかめの個体が多いため初心者向け。
- クロコオロギ(ジャマイカンフィールドコオロギなど):体が硬めで動きも素早く、やや上級者向け。
与える際は、ウーパールーパーの口の大きさに合ったサイズを選ぶことが重要です。目安としては、
- 成体のウーパールーパー → 成虫〜Lサイズ程度
- 幼体や小型個体 → S〜Mサイズ程度、または幼虫や羽化直後の個体
体長に対して大きすぎる個体は、詰まらせたり消化不良の原因になるため注意しましょう。
1回に与えるコオロギの数
ウーパールーパーの個体サイズや体調によっても異なりますが、1回の給餌で与えるコオロギの数は以下を目安にしてください。
- 小型個体・幼体:1〜2匹程度(小さめのサイズ)
- 中型〜成体個体:2〜3匹程度(中〜大サイズ)
あくまで「おやつ」や「ごほうび」として使う補助食なので、毎回の食事で与える必要はありません。
週1〜2回のペースで、他のエサと併用しながら取り入れるのがベストです。
ピンセットを使って与える
ウーパールーパーは、目で見るよりも水中の動きを感知してエサを見つけるタイプの生き物です。
そのため、水面に浮かぶだけのコオロギには反応しないこともあります。
ピンセットを使って、水中でゆらゆらと動かして見せると、反応して食いつきやすくなります。
コオロギを水中にそのまま放り込むよりも、ピンセットでコントロールするほうが確実で安全です。
冷凍コオロギを活用する
生きたコオロギは扱いが難しく、場合によっては水面に浮いたまま動かなくなり、ウパが見つけられずに腐敗→水質悪化というトラブルにつながることもあります。
その点、冷凍コオロギなら保存もしやすく、あらかじめ殺菌処理されているため寄生虫や農薬の心配も少なくなります。使うときは解凍して、ピンセットで与えるのがベストです。
足や羽を取り除くと安心
コオロギの足や羽は意外と固く、腸に詰まる原因になりやすい部分です。
特に小型の個体や幼体に与える場合は、後ろ足や羽を取り除くひと手間をかけることで、安全性が高まります。
また、大きすぎる個体は丸ごと与えず、半分に切るなどサイズ調整をしてあげると安心です。
頻度は「たまのおやつ」程度にとどめる
コオロギはあくまで補助的なエサです。与えすぎると栄養が偏ったり、人工飼料を食べなくなる可能性があります。
与える頻度としては、週1〜2回、1〜2匹程度が目安。特に嗜好性が高いため、「ごほうび」や「食欲が落ちたときの刺激」として使うのが理想的です。
6. コオロギ以外のおすすめ昆虫系エサ
ウーパールーパーに与える昆虫系のエサとして、コオロギ以外にも使えるものはいくつかあります。
ここでは、実際に使用されることがある代表的な昆虫系エサを紹介します。
ミルワーム(ゴミムシダマシの幼虫)

白くてニョロニョロとした見た目が特徴のミルワームは、ペットショップなどでも比較的入手しやすい昆虫系のエサです。
- 高たんぱくで食いつきも良好
- 表皮がやや硬く、与えすぎやサイズに注意が必要
- 活き餌よりも、冷凍や乾燥処理されたもののほうが安全
ウーパールーパーにミルワームを与える場合は脂質も多いため、「たまに与えるおやつ」として使うのがベストです。

シルクワーム(カイコの幼虫)

シルクワームは、主に爬虫類や両生類向けのエサとして近年注目されているエサです。
- 体が柔らかく、消化によいのが大きなメリット
- 高たんぱく・低脂肪で、栄養バランスも良好
- 活きたものの入手は難しいが、冷凍や乾燥品が市販されている
ウーパールーパーにとっては、コオロギよりも安全性が高く扱いやすい昆虫系エサとしておすすめできます。
ハニーワーム(ハチノスツヅリガの幼虫)

甘い香りで爬虫類や両生類の食欲を引き出すことで知られるハニーワーム。こちらも昆虫系のおやつとして使われることがあります。
- 柔らかくて食べやすい
- 栄養価は高いが、脂質も多めなので与えすぎ注意
- 活きたもの、冷凍、乾燥などさまざまな形で流通している
独特のにおいで反応を引き出すことができるため、食欲不振の個体への補助食として使う人もいます。
7. まとめ:ウパにコオロギの餌は「あり」だけど注意が必要
ウーパールーパーにコオロギを与えることは可能ですが、自然界では食べることのない“イレギュラーなエサ”であるという点を理解しておく必要があります。
コオロギはたんぱく質が豊富で、動きによって食欲を刺激するなどのメリットもありますが、消化のしにくさや栄養の偏り、与え方によるトラブルなど、注意すべきポイントも多くあります。
与える場合は、
- 冷凍または衛生的に管理された個体を使う
- ピンセットで与えるなどの工夫をする
- 足や羽を取り除くなど、消化しやすい形で与える
- 頻度は「たまのおやつ」程度にとどめる
といったポイントを意識しましょう。
また、コオロギ以外にもミルワームやシルクワーム、ハニーワームなど、補助食として使える昆虫系エサもあります。それぞれに特徴や注意点があるため、ウーパールーパーの状態に合わせて上手に使い分けていくとよいでしょう。
ウーパールーパーに昆虫系のエサを与える際は、主食とのバランスを大切にしながら、無理のない範囲で楽しむことがポイントです。
\ ついでにこれも読んでいけ。 /
いや、読んでくださいお願いします(土下座)









