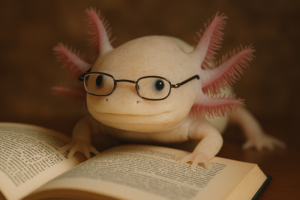ウーパールーパーが水面に浮いたまま沈まない状態を見ると、「これって病気?」「いわゆる“ぷかぷか病”では?」と不安になりますよね。
飼育者の間で 「ぷかぷか病」 と呼ばれるこの症状は、正式な病名ではありませんが、ウーパールーパーが自力で沈めなくなる状態 をまとめて指す俗称です。
実はこの「ぷかぷか病」、すべてが重い病気というわけではなく、
・肺呼吸で空気が入っているだけの一時的なもの
・便秘や消化不良によるガス溜まり
・水温や餌が原因の軽度な体調不良
・内臓や浮力バランスに関わる深刻な異常
など、原因によって緊急性が大きく異なります。
見た目が似ていても、
「様子見で回復するケース」と
「早めに対処しないと命に関わるケース」
がはっきり分かれるのが、この症状の怖いところです。
この記事では、ウーパールーパーの ぷかぷか病(浮く症状) について、
・なぜ浮いてしまうのか
・病気なのか、自然な行動なのか
・自宅でできる正しい対処法
・動物病院に連れていく判断基準
を、飼育者目線で分かりやすく解説します。
\ ウーパールーパーの飼育に関する /
まとめページは以下より
ウーパールーパーの飼育まとめ
ウーパールーパーのぷかぷか病とは?浮く症状の正体

ウーパールーパーの「ぷかぷか病」とは、体が水面に浮いたまま沈めなくなる状態 を指して、飼育者の間で使われている呼び方です。
これは正式な病名ではなく、「ウーパールーパーが浮いてしまう症状」をまとめて表した俗称になります。
よく誤解されがちですが、魚に見られる浮き袋病とは別物です。
ウーパールーパーは魚ではなく両生類のため、浮袋という器官自体を持っていません。
では、なぜ浮いてしまうのでしょうか。
ぷかぷか病の正体は、大きく分けると次のような状態です。
まず多いのが、体内に空気やガスが溜まり、浮力のバランスが崩れているケースです。
肺呼吸で吸い込んだ空気、消化不良や便秘によって腸内に発生したガスなどが原因で、体が軽くなり沈めなくなります。
次に、消化器官や内臓の不調が関係している場合があります。
腸の動きが鈍くなったり、感染症などで正常なガス排出ができなくなると、結果として浮いてしまうことがあります。
さらに、水温・水質・ストレスといった飼育環境の乱れも、ぷかぷか病の引き金になります。
特に水温が高すぎる状態では代謝が乱れ、消化不良やガス溜まりが起きやすくなります。
重要なのは、「ぷかぷか病=すべて重い病気」ではない という点です。
一時的な肺呼吸や軽い消化不良による浮きであれば、絶食や水温調整だけで自然に治ることも珍しくありません。
一方で、
・逆さまに浮く
・片側だけが浮いて傾く
・自力で姿勢を戻せない
といった状態が見られる場合は、内臓の異常や重度の体調不良が隠れている可能性もあります。
そのため、ぷかぷか病は「浮いているかどうか」ではなく、「姿勢・食欲・回復傾向」を総合的に見て判断する症状
と考えることが大切です。
このあと、ぷかぷか病につながる具体的な原因と、それぞれの正しい対処法について詳しく解説していきます。
ウーパールーパーが浮く原因とそれぞれの対処法を解説!
肺に空気が入っている
ウーパールーパーはエラ呼吸だけでなく肺でも呼吸できます。
そのため、水面に顔を出して空気を吸いこむことがあります。肺に空気がたまると、その分だけ浮力が強くなり、水中に沈みにくくなることがあります。
対処法
肺呼吸で吸い込んだ空気なら、しばらくすると自然に沈みます。
元気に動いていて食欲もあるなら、無理に沈めようとせず、様子を見守るだけで大丈夫です。
休憩やリラックス中
ウーパールーパーは活発に動いているときだけでなく、水面近くや底でじっとしている時間もあります。
特に昼間はあまり動かず、リラックスしている可能性も。水面にじっと浮いているだけで、食欲や排泄に問題がなければ、自然な行動の一部かもしれません。
対処法
水面に浮かんでじっとしていても、リラックスしているだけなら問題ありません。変に触ったり、水を揺らしたりせず、静かにしてあげましょう。
ガスが溜まっている(浮袋の異常)
腸内にガスが溜まると、体が軽くなって浮きやすくなります。
浮袋(本来は魚のバランスを取る器官)ではなく腸や胃のガスが原因であることも多く、「浮き袋病」と似た状態になります。
ウーパールーパーは魚ではありませんが、ガスの影響で浮力バランスが崩れることがあります。
対処法
まずは1〜2日、エサを与えずに様子を見ます。ガスが溜まっている場合、絶食が一番の対処法です。
加えて、水温を20℃前後に保ち、代謝を落ち着かせることで自然とガスが抜けていくことがあります。
便秘
便がうまく出ないと、腸に溜まった老廃物が発酵し、ガスが発生します。これにより体が浮いてしまうことがあります。
特に底に沈むタイプの餌を与えず、水面ばかりでエサを食べさせていると便秘になりやすいです。
対処法
絶食でエサを与えず腸を休ませ、しばらく様子を見ましょう。
便秘が原因の浮きの場合、水温を20〜22℃に少しだけ上げると排泄が促進されることがあります(25℃以上は逆効果なので注意)。
過剰な空気を飲み込んだ
水面でエサを食べるときに、誤って空気も一緒に飲み込んでしまうことがあります。
この空気が胃や腸に入り、浮いてしまう原因になります。
急いで食べる個体や、空腹状態が続いていた個体に多く見られます。
対処法
浮いてくる餌(フレークや水面に浮くペレット)は避けて、沈下性の餌(赤虫や沈む専用ペレット)に変えましょう。また、ピンセットやトングで水中に沈めて与えると、空気を飲み込みにくくなります。
水温が高い
ウーパールーパーの適正水温は18~22℃くらいです。25℃を超えると代謝が急激に上がり、腸内発酵が進んでガスが発生しやすくなります。
さらに、高温そのものが体調不良やストレスの原因にもなるため、注意が必要です。
対処法
25℃を超えると体調を崩しやすいので、夏場は水槽用の冷却ファンや、凍らせたペットボトルを使って冷却します。直射日光を避け、水槽はなるべく風通しの良い場所に設置しましょう。
消化不良
与えた餌がうまく消化できないと、腸内に腐敗物が溜まり、ガスを発生させることがあります。
特に低品質な餌や、与えすぎ、解凍が不十分な冷凍赤虫などは消化不良の原因になります。
餌の種類や量、与える頻度にも気を配ることが大切です。
対処法
与えている餌が脂っこい、硬い、大きい場合は小さく切ったり、より消化しやすい餌に切り替えると改善することがあります。
また、1回の量を減らして、1日1回のみにするのも効果的です。
誤ったエサ(消化しにくいもの)
人間の食べ物や肉類、脂っこいもの、炭水化物の多い餌などは、ウーパールーパーの消化器に負担をかけます。
特に初心者がやりがちなのが、「赤虫だけに頼る」「ご褒美に変わった餌を与える」などで、これが原因で浮きやすくなることもあります。
対処法
人間の食べ物やペット用の別の餌(犬猫用、熱帯魚用など)は絶対に与えないようにします。
ウーパールーパー専用の餌か、冷凍赤虫、イトミミズなどに限定すると安心です。
ストレスや体調不良
ウーパールーパーは環境変化に敏感な生き物です。
水換えの頻度が不安定だったり、物音や光、振動が激しい場所で飼われていると、ストレスがたまり、消化不良や免疫力低下につながります。
結果的に浮く症状が出ることがあります。
対処法
水槽を人通りが少なく、照明や音が落ち着いた場所に移動させましょう。フィルターの音、水の流れ、周囲の刺激などもストレス源になります。
レイアウトはシンプルで隠れ家(シェルター)があると落ち着きます。
感染症
腸炎や内臓の感染症など、体の中に病気があると、正常なガスの排出ができず、浮いてしまうことがあります。
また、浮袋に直接関わる細菌感染も可能性として考えられます。急に浮き方が変わった、元気がない、食欲もないといった場合は病気を疑いましょう。
対処法
浮き方が極端(逆さま・回転・傾きが強いなど)で、元気がなく食欲も落ちている場合は感染症の疑いがあります。爬虫類や両生類を診られる獣医さんに相談しましょう。可能であれば別の容器に隔離して経過観察をします。
浮袋の病気や損傷
浮袋自体が傷ついている、または病気で機能しなくなっていると、浮力の調整ができず、水面に浮いたままになったり、逆に沈んだままになることもあります。
片側だけ浮いて傾いていたり、逆さまになっている場合は浮袋に問題があるかもしれません。
対処法
浮袋の損傷は回復に時間がかかることがあります。
絶食、低水位(体の半分が水から出ない程度に)での飼育、ストレスを減らす環境づくりなど、じっくりと付き合う必要があります。自然治癒が見込めない場合は、専門家の判断が必要です。
水質悪化(アンモニアや亜硝酸が多い)
水質が悪くなると、体調に直結します。
特にアンモニアや亜硝酸の値が高いと、呼吸器や内臓にダメージが生じ、結果として浮くなどの異常行動が現れることがあります。
定期的な水質チェックと水換えが重要です。
対処法
まずはpH、アンモニア、亜硝酸などの値をチェックします(試験紙や試薬を使用)。悪化していれば3分の1〜半分程度の水を交換し、フィルターを点検・掃除します。底砂の汚れも要チェックです。
フィルターの水流が強すぎる
ウーパールーパーはあまり泳ぎが得意な生き物ではありません。
強い水流に逆らえず、水面に押し上げられてしまっていることがあります。
フィルターの出口が直接当たっていないか確認し、水流を弱める工夫をすると良いでしょう。
対処法
フィルターの排出口にスポンジや水草を設置して、水流を拡散させるとウーパールーパーが快適に過ごせます。または、出力を調整できるフィルターに変更するのも手です。
水位が浅すぎる
水深が浅いと、必然的に「浮いている時間」が長く見えてしまうことがあります。
ウーパールーパーはある程度の水深(20〜30cm以上)があった方が、自然な動きができます。特に体の大きな個体には深さが必要です。
対処法
ウーパールーパーは水深がある方が自由に動けます。
20〜30cm程度の水位があると浮きっぱなしにもなりにくく、自然な行動がしやすくなります。深すぎると逆に疲れる場合もあるので、個体のサイズに合わせて調整しましょう。
ウーパールーパーの中には「浮くのが好き」な個体もいる
ウーパールーパーにも個体差があり、「水面近くでじっとしているのが好きな子」や「底で動かず休むのが好きな子」がいます。
性格や習性の違いで、水面にいる時間が長い個体は「浮くのが好きなのかな?」と感じられることがあります。
特に、若い個体や小柄な個体では浮力が強く、体のバランスがとりやすいため、水面近くをぷかぷか漂っている時間が長くなることがあります。
これは、本人(本人?本魚?)にとって楽な姿勢だったり、肺呼吸をしやすい場所だからという理由もあるでしょう。
また、エサを水面でよく与えられている個体は、水面=ごはんの場所と学習して、好んで上にいるようになる場合もあります。
これも一種の「浮くのが好き」という行動のように見えるかもしれません。
対処法
ただし、「いつも浮いているからこの子は浮くのが好きなんだ」と思って放っておいた結果、実はガスが溜まっていた、消化不良だった、病気だったということもあります。
なので、「浮くのが好きなように見える」ときも、姿勢や食欲や排せつ物などを注意深く観察するようにしましょう。
死後の可能性
ウーパールーパーが死後浮く可能性もあります。
しかしウーパールーパーは死後すぐに浮くわけではなく、亡くなってすぐは沈んでいることが多く、時間経過によって浮いてくる場合があります。
ウーパールーパーが死亡すると、体の機能が止まり、筋肉もゆるみます。
最初のうちは体内に大きなガスなども発生していないため、重みで沈んでいることがほとんどです。
しかし、時間が経つと体内で腐敗が始まり、細菌の働きによってガス(主にメタンや二酸化炭素など)が発生します。
すると、そのガスによって浮力が増し、体が水面に浮いてくるという現象が起きます。
これはウーパールーパーに限らず、魚や両生類全般に共通する現象です。
対処法
生死を明確にして、状況に応じて対応してください。

動物病院に連れていく・自宅で経過観察かの判断基準
緊急性が高く動物病院の獣医に診てもらった方が良いケース
- 逆さまに浮いている(お腹が上)
- 片側に大きく傾いて浮いている
- クルクル回って泳ぐなど、明らかにバランスを失っている
- 呼吸が苦しそう(口を頻繁にパクパク)
- まったくエサを食べない日が2〜3日以上続いている
- お腹が異常に膨らんでいる/出血・ただれがある
- 排泄が全く見られない(便秘+浮き+食欲不振)
- 皮膚が白く濁っている、ふやけている
- 動かずに長時間水面に浮いたまま(だらりとした姿)
- 手足やエラがしぼんだり、変形してきた
これらは感染症・内臓疾患・浮袋の障害などの可能性が高く、早めの対応が重要です。
自宅での経過観察をできる状態
- 水面近くに浮いているが 姿勢は安定している
- しばらく浮いていても たまに自力で泳いで沈めている
- 食欲があり、排泄も確認できる
- 水換えや温度管理をすると改善してきた
- 浮いてはいるが、元気に動き回っている
この場合は、絶食・水温調整・餌の見直し・水質管理などの対処で自然回復することが多いです。
ワンポイントアドバイス
「ウーパールーパーが浮く=病気」とは限りません。
複数の症状の組み合わせで状況を判断することが大切で特に「食欲」と「姿勢」のふたつが大きなヒントになります。
判断に迷ったときは、写真や動画を撮って、獣医やアクアショップに見せると助けになります。
ウーパールーパーを動物病院に連れていく際の方法
対象病院を探す
ウーパールーパーを病院に連れていく場合、まずは両生類に対応できる動物病院を探す必要があります。
お分かりだと思いますが動物病院や獣医さんの中でもウーパールーパーは比較的レアな動物です。
犬猫を診てくれるペットショップは多いですが、爬虫類や両生類を診てくれる病院は少ないです。
一般的な動物病院では診察対象外となっていることが多いため、「ウーパールーパー 診察 〇〇市」といったキーワードで検索したり、エキゾチックアニマルを診察している病院を調べたりするとよいでしょう。
また、近くのアクアショップに相談すると、ウーパールーパーに対応している病院を紹介してもらえることもあります。
見つけたら、事前に電話で「ウーパールーパーの診察が可能かどうか」を確認しておくと安心です。
診察の受け方
診察を受ける前には、医師にスムーズに伝えられるように、いくつかの情報を整理しておくとよいでしょう。
たとえば、いつから浮くようになったのか、食欲の有無、排泄の状況、水温や水質の状態、与えている餌の種類や頻度、水槽のサイズや設備(底砂やフィルターの有無)、気になる様子(皮膚の色や動き方など)などです。
これらの情報をメモ帳やスマホのメモアプリにまとめておくと、獣医師も状況を把握しやすくなります。
ウーパールーパーの持ち運び方
実際に連れていく際は、ウーパールーパーの体に負担をかけないような持ち運び方法を選びます。
移動中の衝撃や揺れをやわらげるため、小型のプラケースやしっかりしたタッパーなど、ウーパールーパーの体が動いてもぶつかりにくい容器を使いましょう。
水は普段飼っている水槽の水を使用し、量は体が沈む程度の少なめにしておくと、揺れたときに水が跳ねたり、呼吸が苦しくなるのを防げます。
また、容器のフタは完全に密閉せず、空気が入るようにしておきましょう。
ふたに小さな穴を開けるか、軽くふたを乗せる程度が理想です。
寒い季節であれば容器をタオルで包んで保温し、暑い季節であれば凍らせたペットボトルや保冷剤をタオルで巻いて一緒に持ち運ぶなど、水温の変化に配慮してあげてください。
いずれの場合も、直接ウーパールーパーに冷却材や保温材が触れないように注意します。
車や自転車で移動する際は、直射日光が当たらない場所に容器を置き、なるべく静かに、揺らさずに運びます。
助手席の足元や膝の上など、安定した場所が望ましいです。
移動中の音や振動もストレスになるため、できるだけ静かな環境を保つようにしましょう。
診察後
病院で診察を受けたあとは、すぐに元の水槽に戻すのではなく、落ち着ける環境でゆっくり休ませてあげることが大切です。
移動と診察によって大きなストレスを受けている可能性があるため、静かな場所で安静にさせましょう。
病院によっては「ウーパールーパーの診察はできません」と断られることもあるため、やはり事前に電話で確認しておくことがとても重要です。
準備と配慮をしっかり行うことで、ウーパールーパーにとっても安心できる診察体験に近づけることができます。
ウーパールーパーが浮く原因と対処法【まとめ】
ウーパールーパーが浮いたままにならないようにするための予防策は、以下の2点です。
・浮くタイプの餌を与えない。
・餌をやる際は腹八分目程度の量にしておく。
また、もし浮いて戻れなくなってしまったら、次のように対応して様子をみましょう。
・水槽内にメッシュでできた箱などを設置して浅い場所を作る。
・沈むタイプの餌を少しずつ与えて様子を見る。
特に消化不良が原因だと助からない場合も多いので、餌の与えすぎにはくれぐれも気をつけましょう。
\ ついでにこれも読んでいけ。 /
いや、読んでくださいお願いします(土下座)